
Yahooニュースに、ガソリン税の暫定税率廃止について、当事務所から記事を掲載いたしました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a2e3c306979664f06cf9fcbce0986c826a71ba30



Yahooニュースに、ガソリン税の暫定税率廃止について、当事務所から記事を掲載いたしました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a2e3c306979664f06cf9fcbce0986c826a71ba30



※ 2025年1月13日現在の情報です。
日本では、一定の条件を満たすと出国税が適用されることがあります。この制度は、資産を海外に移転し、日本国内で課税されるべき利益が未払いのままにならないようにするためのものです。しかし、仮想通貨に関しては、この出国税の対象外となっています。
出国税は、一定の基準を超える資産を保有し、かつ居住者の地位を離れる場合に課税される制度です。対象となるのは、以下のような金融資産です:
2025年1月現在、仮想通貨は有価証券として扱われてないことから、出国税の対象となっていません。
仮想通貨は2025年現在、出国税の対象外とされていますが、今後の税制改正によって変更される可能性があります。最新情報を確認し、適切な資産管理を行うことが重要です。

はじめに
相続税の負担軽減を目的として、海外への移住を検討する方は少なくありません。日本に長く居住しなければ、相続税法上の「非居住者」となり、課税対象となる資産が限定されるケースもあるためです。例えば、シンガポールやドバイ等への移住があげられます。
しかし、相続税対策として海外へ移住しても、新天地での生活が思ったような快適さをもたらすとは限りません。元ベトナムの駐在員だった視点で記事にしました。
移住当初は「新鮮で楽しい」しかし徐々に生まれる不満
当初は海外生活に心踊らせ、娯楽や観光地を存分に楽しんでいました。しかし、数ヵ月も経つと、娯楽施設や遊び場は限られ、次第に飽きが生じます。
また、南国の場合は、はっきりとした四季がなく、1年を通じて大きく変わらない気候が、人によっては退屈になったりまします。1年中、Tシャツ、短パン、サンダルの生活です。
海外移住を断念・帰国する主な理由
家族・友人との距離:
海外移住は、これまで築いてきた家族・友人関係との物理的距離を大きく広げます。オンラインツールでコミュニケーションがとれる時代とはいえ、直接会える距離にいない寂しさは残ります。
言語の壁と現地社会への溶け込み:
英語が通じる都市への移住でも、ローカルコミュニティでの生活を満喫するにはそれ相応な言語力が欠かせません。
医療・政治情勢への不安:
若い頃には気にならなかった健康問題も、年齢を重ねると重大な関心事となります。海外で医療費が高額になるケースや、政治的・社会的な不安定要素があると、将来への不安が募りやすくなります。
相続税対策として海外移住を考える場合、純粋な税務面での有利性だけではなく、移住先での生活の質や家族関係、健康面、将来への展望など多角的な視点が必要です。
もし、海外移住を考えている場合、移住先にお試しで、2年ほど住んでみることをオススメします。

生命保険金は、被保険者の死亡時に受取人が受け取る財産であり、通常は相続税の対象です。ただし、一定条件下では非課税枠が適用され、これを活用することで相続税の負担を軽減できます。本解説では、非課税枠の仕組みと活用法を簡潔にまとめます。
【非課税枠の概要】
非課税枠は相続税法に基づく優遇措置で、受取人の属性や契約内容に応じて適用されます。
1. 受取人の属性
■ 配偶者: 基礎控除が大きく課税リスクは低いが、非課税枠が少ない場合があります。
■ 子供: 非課税枠が大きく節税効果が期待されます。未成年の場合、親が財産を管理できます。
■ 孫: 原則として非課税枠が適用されず、2割加算などの影響で税負担が増大します。
2. 契約内容の見直し
契約金額や受取人の調整を行うことで、相続税の負担をさらに軽減できます。
【非課税枠の活用方法】
非課税枠を最大限活用するには、以下のポイントが重要です。
1.受取人の選定
受取人を配偶者や子供とすることで、節税効果を高められます。孫を受取人にする場合は税負担の増加リスクに注意が必要です。
2.契約内容の見直し
保険金額や受取人設定の変更を通じて、税制上のメリットを最大化できます。
【主要ポイント】
上記のとおり、非課税枠については、子供を受取人とすることをメインに検討いただければと思います。
生命保険金の非課税枠は、相続税対策として有効ですが、受取人や契約内容を慎重に検討することが必要です。正しい知識を基に活用することで、相続税の負担を減らし、スムーズな遺産分配を実現できます。

確定申告の準備をされている方もいると思います。今回は、実務上でも誤りがあると言われている生命保険金における確定申告の注意点について、触れたいと思います。
生命保険に係る一時所得は、保険事故が発生した日に収入すべき時期が決まります。そのため、実際に保険金を受け取った時期が後になっても、保険事故が発生した年の所得として確定申告する必要があります。この点に注意しないと、無申告加算税や延滞税の対象になる可能性があります。
例えば、保険事故の発生が12月、保険金の受取が翌年の3月になったケースが注意です。
生命保険に係る一時所得は、保険事故が発生した日に収入すべき時期が決まります。そのため、実際に保険金を受け取った時期が後になっても、保険事故が発生した年の所得として確定申告する必要があります。
生命保険に係る一時所得を確定申告しない場合、無申告加算税や延滞税の対象になるので、注意が必要です。


会計年度の初月にオフィスをリニューアルするために、机や椅子などを会計年度末に納品し、段ボールに入れたまま。会計年度を跨いだりすることがあると思います。
これらは、会計上計上は可能なのです。ただし、税務上は、納品された机や椅子が、年度期間中に利用できるようにしないと、その期間に損金計上をすることができません。ご注意ください。(損金計上は、使用が開始となった翌期)
特に1月~12月決算の会社においては、税務調査においては、12月の最終営業日以後に納品された机や椅子の納品日に属する期間の損金は認められない可能性が高いです。
よって、会計年度末には、備品の納品のタイミングにはご注意ください。

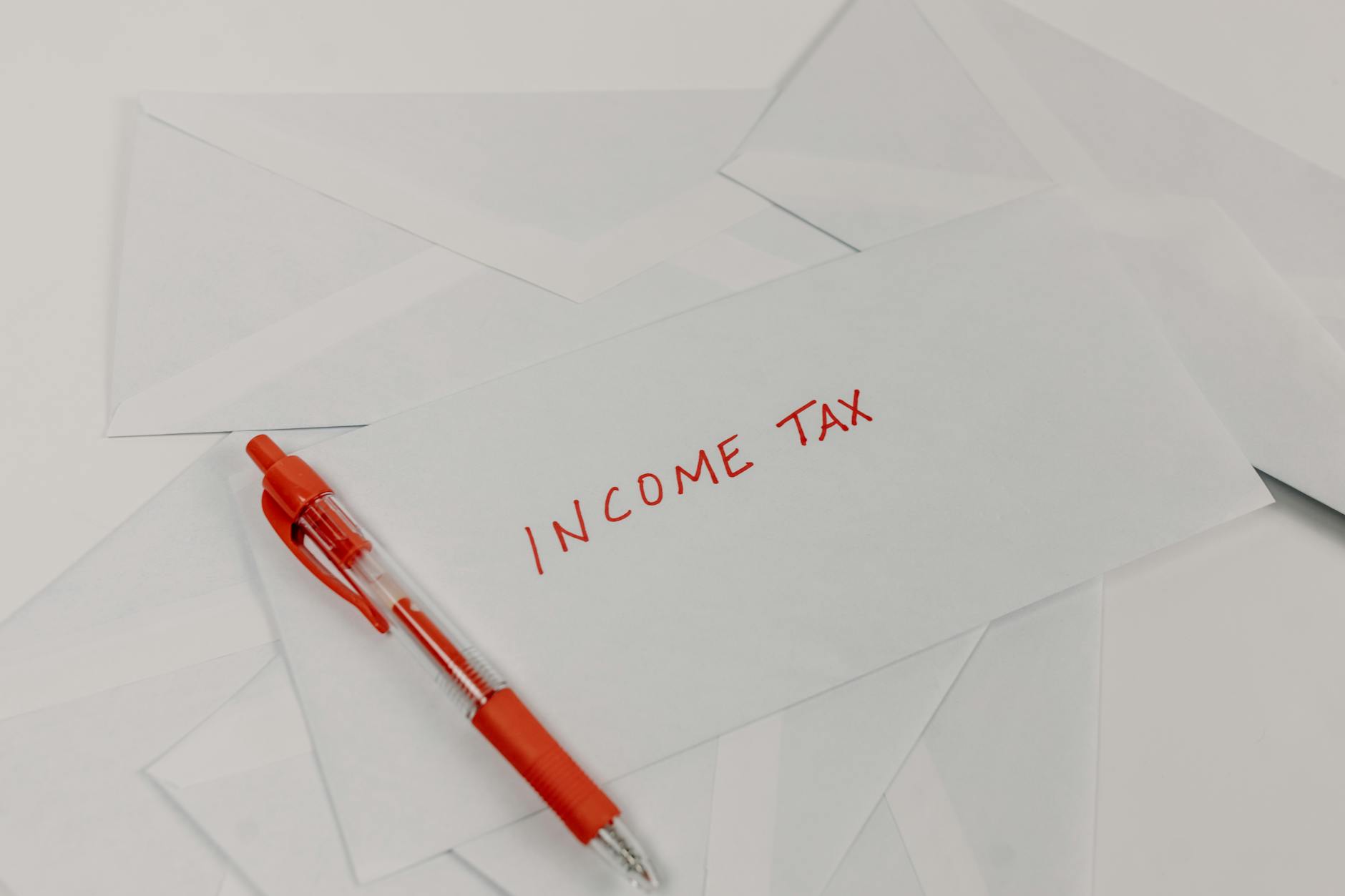
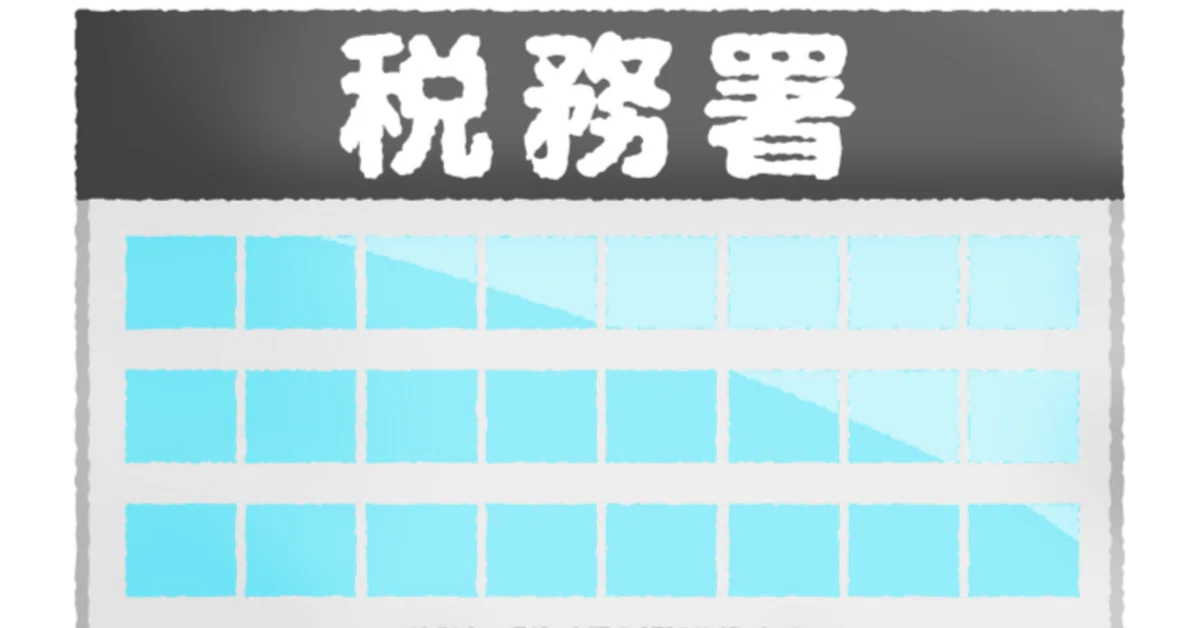
先日、教育系YouTuberのモリテツさんの会社が税務調査を受けたことを、経営者であるモリテツさんが動画をUPされていました。
https://youtu.be/S6f-pU5Rftc?si=S66Tip-yIWaiCcgY
調査の結果、今回、特に大きな問題は無かったとのこと。
日々の経理を適切にされていたうえで、経営者であるモリテツさん自身が、会社の経営状態を把握され、調査官に自らの言葉で、分かりやすく説明されたことが、今回の結果の要因だと思いました。
私も過去、日本とベトナムにおいて税務調査の現場に、経理担当者として対応し、大きな問題はありませんでした。
その際の共通点は、事業所の責任者が、自らの言葉で調査官に分かりやすく説明したことを覚えています。
モリテツさんの今回の動画から、税務調査は企業経営者にとっては避けられないものですが、事前にしっかりと準備しておけば、スムーズに乗り切ることができるということが分かります。
また、税務調査は企業の経理体制を強化する良い機会にもなるため、積極的に取り組むべきだという考え方も示されています。
この動画を通して、税務調査に対する理解を深めることができると思います。特に、これから事業を始める人や、既に事業を行っている人にとって、この動画を見ていただくことで、税務調査に関する理解を深められると思いました。